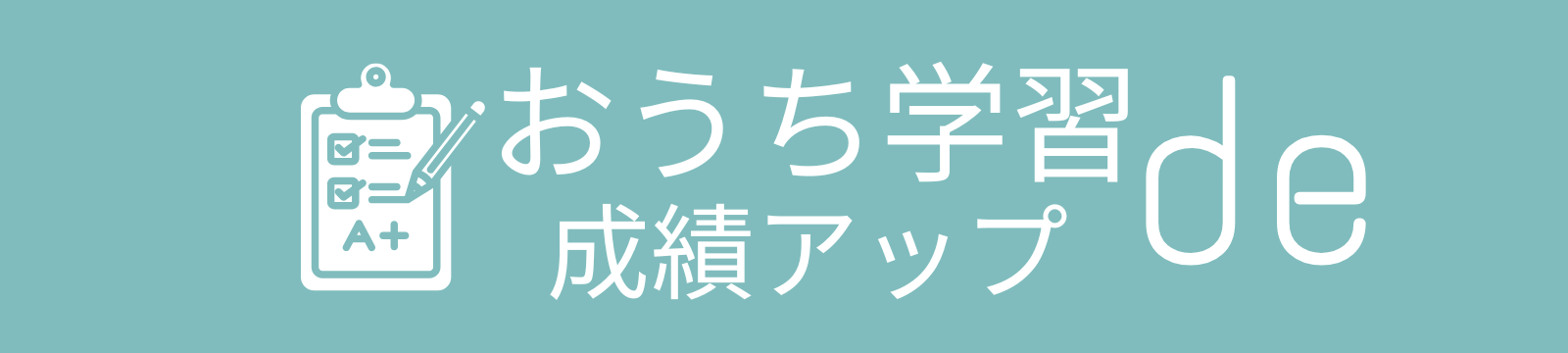私が神戸大学に塾なしで現役合格した方法!共通テスト8割をとった田舎でもできる独学勉強法

塾に通わずに大学受験を成功させることは可能なのでしょうか?

私は田舎の高校に通いながら、塾なし・独学・受験情報ゼロで共通テスト8割をとり神戸大学に現役合格しました
独学にはコストがかからないというメリットがありますが、自己管理や学習環境の面でハードルもあります
そこで本記事では、私が実践した独学の勉強法や、田舎でも使える学習リソース、独学のデメリットとその対策について詳しく解説します
塾なしでも志望校合格を目指せるよう、具体的な勉強法を知りたい方はぜひ参考にしてください!
<この記事の信頼性>
・高校3年間塾なしで神戸大学に現役合格
・共通テストは過去最高点(720点)獲得
・共通テスト生物100点、化学97点
・学校の教材のみで学習
塾なし・独学でも神戸大学に現役合格!私が実践した勉強法



早速、私が大学受験に向けて実践した勉強法を紹介します
いくつかあるので、各パート毎にわけて解説していきます
準備編:独学で合格するための準備
- 参考書は1冊で十分
- テストや模試は積極的に受ける
① 参考書は1冊で十分
市販の参考書は数多くありますが、あれこれ手を出すよりも、1冊を徹底的にやり込む方が効果的です
私は各教科につき1冊の参考書を選び、テスト前はそれだけをみるようにしました
私の場合は学校で配られた参考書もしくは先生オリジナル教材があったので、それを使用していました



コンパクトサイズの方が持ち運びしやすいのでオススメです
参考書を購入する場合は、実際に中身をみて「見やすいな」と直感的に思うものを購入するのが良いです
参考までに私が使用していた参考書をご紹介します
- 数学:青チャート
- 生物:アクセス生物
- 化学:先生オリジナル教材
- 地理:先生オリジナル教材
但し、当時の私は学校以外の参考書を買うという考えがなかったので、上記の参考書になっただけです
今はもっと自分に合った本やわかりやすい本があると思うので学校の参考書が微妙だなと思う場合は本屋さんで自分が良いと思う参考書を1冊買いましょう!
国語、英語は学校から配布された単語帳のみで参考書などは使用していませんでした
② テストや模試は積極的に受ける
模試やテストは、実力を試す絶好の機会です
実際に勉強した知識を試験で出せているかを確認することで自分の勉強法を見つめなおすことができます



私の学校は月1くらいのペースで模試があったので、自分が苦手な分野などが明確になり、とても良かったです
勉強して理解していたつもりでも試験になると解けない・・ということが結構あります
進学校であれば定期的に模試を受けると思うので、そこでしっかり自分が解けていない単元を確認するようにしましょう
模試があることで「締め切り効果」が生まれ、勉強のモチベーションになります
また模試を受ける際には毎回「目標」を立てることが大切です
例えば、今回の模試では「三角関数の単元を解ききる」など、毎回目標を設定し、それに対してどうだったかの復習が大切です
模試全体の結果よりも目標に対してどうだったか、模試を振り返り次どうしていくかを毎回設定しましょう
勉強編:独学で効率よく学ぶための勉強法



それでは最も大切な勉強法について解説していきます!
私がやっていた勉強法はいたってシンプルです
今から説明する3つをひたすら繰り返した結果、塾なしでも共通テストで8割、生物100点、化学97点を取ることができました
- テストや模試は必ず復習しもう一度解く
- 新しく学んだ知識は日付とともに参考書に追加する
- 単語は調べるたびに日付を記入
① テストや模試は必ず復習しもう一度解く
模試やテストの復習は、学力を伸ばす最大のポイントです
模試を受けて終わり、点数や判定だけみて「今回は良かった、悪かった」というだけでは非常にもったいないです



模試で間違った問題は解説を読み、理解した上でもう一度必ず解くようにしましょう
私は間違えた問題を解き直し、なぜ間違えたのかをノートにまとめました
- 間違えた問題をノートに貼る
- 解説を読む
- もう一度解きなおす
- ポイントを書き込む
- 類似問題がある参考書のページを記入しておく
解きなおす際は何も見ずに最初から最後まで解き、できなかった場合は再度解説を読み最初から解くということをやっていました



間違った問題は1度解説を読んだだけでは理解できないことが多いので、きちんと理解できているかを確認するために最初から自力で解きなおしてみるということをすることが大切です
次回の模試やテスト前にノートを優先的に見直すことで効率よい復習ができます
ノートはルーズリーフなどで単元ごとにまとめても良いですし、問題をスマホなどで撮影してフォルダや暗記アプリなどにまとめておくのも良いと思います
どちらにしても1つに集約するのがポイントです
② 新しく学んだ知識は日付とともに参考書に追加する
勉強を進める中で新たに学んだことや間違ったところは、そのままにせず、参考書に書き込みました
参考書に書かれていない知識や問題に出会った際には参考書に書き込むことで自分が学んだ知識を全て1冊の参考書に集約し取りこぼしがないようにしていました



だんだん書き込むスペースがなくなってきたりすると思うのですが、その際は大きめの付箋に書いて参考書に貼るようにしていました
その際に日付を記入することで、後から振り返った際に「この時期に学んだんだ」と思い出しやすくなります
私はポストイットの正方形の付箋を使用していましたが、今はもう少し大きいサイズもあるみたいです
私は生物の勉強は学校で配布された「アクセス生物」を使用していました
アクセス生物はコンパクトサイズの参考書のため書かれていない情報も多いです
書いていない知識を他の参考書で調べた際はその情報をアクセス生物に書き加えたり、付箋を使用して間違った問題を書き加えたりしていました
③ 単語は調べるたびに日付を記入
英単語や古文単語を覚えたり調べるとき、単語帳を使用すると思います
その際に調べた日付を記録しました
日付が3回書き込まれたら、その単語のページに付箋などの目印をつけるということをしていました
私は面倒くさがりだったのでドッグイヤーしていました



3回以上調べたということは自分が覚えるのに苦労するかつ良く出てくる単語ということがわかります
この方法は国語の先生に言われてやり始めたのですが、短い期間で何度も調べたりしていると自分でも「なんで全然覚えないんだよ~」とか言いながら日付を書いていました
これは「勉強が見える化」して良いなと思ったので英単語でも同じようにしていましたし、参考書などでも日付は必ず書くようにしていました
テストとテストの間は10分ほどしかないので、何をみたら良いかわからなくなってくると思うのですが、これをしておくと自分が見るべきところがすぐにわかるのでテスト前の復習に効果的です
試験編:試験本番で実力を発揮するための対策



ここでは試験の取り組み方について紹介します
せっかく勉強をしても試験でその力を発揮できなければ中々結果は出ません
そのためにも試験での取り組み方を2つ紹介します



実際に私がやっていた方法です
- 模試のルーティンを決めておく
- 試験中の自分を客観視する
① 模試のルーティンを決めておく
試験では必ずルーティンを決めておくことが大切です
ルーティンを決めておくことでいつでも自分の力の最大値を発揮できるようになります
ルーティンは試験でやってしまいがちなミスを防ぐための方法なので、自分に合うやり方が良いですが、参考までに私が実際にやっていたルーティンを紹介します
- 最初に名前を書く
- 問題用紙を確認する
- 飛ばす問題は解答用紙にも目印をする
- 最後の5-10分は見直しにあてる
- 見直す際は簡単な問題を中心に見る
最初に名前を書く
試験開始の合図でまずは解答用紙に名前などの必要事項を記入しましょう
当たり前すぎることだと思いますが、試験ではいつもしないようなミスをしてしまいます
開始と同時に問題を解き始めてしまうと、試験に夢中になり名前を書くの忘れてた!ということは実際に起こりえます
名前以外にも受験番号など必ず記入しなければいけない項目は最初に記入しておきましょう
問題用紙を確認する
次に問題用紙を確認し、最初から最後までパラパラとみていきましょう
問題をみれば「この問題は時間かかりそう」「これは解けそう」などなんとなくわかります



その上で時間配分を決めて解き始めることで最後まで解けなかったという事態を防ぐことができます
また、共通テストなどでは自分が解く問題ではないページや選択問題も含まれています
必ず全部みて自分が解く問題がきちんと含まれているか、どの問題を解くのかを確認しておきましょう
解く問題が決まったら解かない問題には「バツ」を付けるなどしてパッと見てわかるようにしておくと、時短になりオススメです
飛ばす問題は解答用紙にも目印をする
実際に問題を解いていくと、必ず難しい問題に出会います
時間に余裕がある場合なら少しだけ解いてみてスムーズに答えにたどり着けそうなら良いですが、予定より時間がかかりそうなら後回しにして他の必ず解ける問題を解いた方が結果的に点数が上がります



その際に要注意なのが飛ばした問題の解答欄に次の問題の解答を書いてしまい、その後が1つずつずれてしまうというミスです
最後の5-10分は見直しにあてる
最後の5-10分は必ず見直しにあてることも大切です
最後まで解けていなくても終了間際5分になったら必ず名前記入の見直し、解いた問題の見直しをするようにしましょう
見直す際は簡単な問題を中心に見る
見直す際には難しい問題よりも簡単な問題を中心に見ていくのがオススメです
「最初の方は簡単だから見直さなくても大丈夫」と思っている方は要注意です
試験ではそういったケアレスミスが非常に多く、同じ実力でもそこで点数の差が出ます
試験で点数を上げるためには簡単な問題を確実に取ることが大切なので、見直す際は「どこか間違えているんじゃないか?」と自分自身を疑ってみていきましょう
② 試験中の自分を客観視する
試験中に焦ってしまうと、普段の実力を発揮できません
私は難しい問題に出会ったときや焦っているときには「この問題難しすぎるなぁ~(笑)」「今自分めっちゃ焦っているな、計算間違いしそうだな」と客観視することで心を落ち着かせていました
メンタル編:独学を続けるためのコツとメンタル管理



ここでは勉強を続けていくうえでのメンタル管理について紹介します
受験期には思うようにいかないことの方が多いです
私自身、気を抜くとすぐにさぼってしまったり、試験が近いのに勉強せずに寝てしまったりしていました
そんな私でも独学で勉強を続けられたのは定期的に自分でメンタルを管理をしていたからです
ここではどういった心構えで勉強を続けていたかを紹介していきます
- スケジュール通りにいかなくて当たり前
- うまくいかないときは口に出す、紙に書く
- 得意科目で機嫌をとる
① スケジュール通りにいかなくて当たり前
基本的に計画通りにはいきません
計画を立てているときは1番やる気がある状態を想定して立ててしまいます
そのため今日はやる気がでない、集中力が続かない日などは思い通りに進みません



そしてそういう日は結構多いです(笑)
そのため試験日まで逆算してスケジュールを立てることは必要ですし、やるべきことはしっかりやらなければいけません



なのでスケジュールをゆるゆるにするのはオススメしません
しっかりやらなければならないことはスケジュールに書き込み、やる気が1番ある状態でのスケジュールを立てるべきではあります
なので、スケジュール通りにいかないときもあるということを事前に理解しておくこと、そしてその遅れを取り返す必要があるということを理解しておけば自己嫌悪にならずに強を続けられます
② うまくいかないときは口に出す、紙に書く
勉強がうまくいかないときは、悩みを紙に書き出したり、声に出したりすると気持ちが整理されます
私は「今の自分はどこでつまずいているのか?」「何が不安なのか」をノートに書くようにしていました
そうすると自分が今すべきことが見えてきます



書くだけでなく、口に出すことも大切です
心の中で思っていることを口に出すだけでも頭がすっきりします
私は難しい問題が解けなかったり、何度も同じ間違いをしてしまったときなどは「なんでこれ解けないんだろう~」「また同じ間違いしてるよ、いい加減にしてよ~」「どうしたら自力で解けるようになるだろう・・」と言っていました
また解説も口に出しながら指差ししながら読んでみると、ただ目で追うだけよりも理解力が上がったり、解説のどこが理解できていないのかがクリアになります
そうすることで「もしかして、ここってこういうこと?」と急に理解できるようになったり、「よし、もう1回解いてみるか!」と、自然とリフレッシュしてポジティブな気持ちになります
③ 得意科目で機嫌をとる
苦手科目ばかり勉強していると、気分が落ち込みがちです
そんなときは、得意科目を勉強して気分転換をしていました



また15分ほど仮眠をとるのもオススメです
気分転換でSNSみたりyoutubeなどの娯楽に走るのはただの現実逃避で結果的に自己嫌悪に陥る可能性があるのでやめましょう
独学のデメリット3つと、その対処法
今まで独学での勉強法をお伝えしてきましたが、ここでは独学のデメリットとその対処法をお伝えしていきます



実際に独学での勉強は挫折しやすく、やり方を間違えると勉強しても全く成績が上がらない可能性もあります
独学のデメリット
- 自己管理力が必須!スケジュール管理の工夫
- わからない問題をすぐ解決できない
- 進学校とそうでない学校で差がつく
①自己管理力が必須!スケジュール管理の工夫
独学では、勉強計画を自分で立てる必要があります
共通テストだけでも5科目以上ありますし、共通テストと二次試験でも対策が異なります
②わからない問題をすぐ解決できない…どう対処する?
勉強して解説を読んでも理解できないことも多々あります
誰かに聞ける環境がない場合、その問題を解決するために時間を要してしまい塾通いの人よりも勉強のスピードが遅れる可能性があります
③進学校とそうでない学校で差がつく?環境の違いをどう埋める?
進学校では情報量が多く、入試対策などもしっかりやってくれます
学校に通っているだけで自然と勉強のレベルや対策、模試などが受けられる状況ですが、そうではない場合は全て自分で手配しなければいけません
特に模試の申し込みや入試対策など、どうしても進学校との差がついてしまいます
デメリットの対処法
それではデメリットの対処法はどうすれば良いのか・・
それは「信じる人を決める」ということです
その際に「この人の言うことを信じてやりきる」という人を見つけておくことが大切です
そうするとぶれることなく信じて勉強をすることができます



私の場合は学校の先生の言っていることを信じてただひたすらその勉強法をしていました
信用できる先生や授業がわかりやすい先生、言っていることが理にかなっている先生に絞って、その先生の言っている勉強法を他科目でも実践していました
学校の先生でなくても、自分がわかりやすいなと思う参考書の著者が書いている参考書を一通り揃えたり、解説がわかりやすいyoutube動画を見たりなど、自分が良いと思う人を見つけられればOKです
【まとめ】塾なし・田舎でも工夫次第で合格は可能!
塾に通わなくても、計画的に勉強し、適切な勉強をすれば現役合格は可能です
志望校合格のために限りある時間を有効に活用し、成績アップのためにひたすら努力し続けることが大切です
私自身の経験が、独学で頑張る受験生の参考になれば幸いです